みなさんこんにちは、ひでえぬです。
放送大学の面接授業「心理学実験」の2日目を迎えました。
昨日と違って今日は寝坊もせず、きちんと筋トレしてから学習センターに向かいます。


教室は昨日と変わらないことを確認してから、会場へ向かいます。
9時15分過ぎには会場につきました。通常だと開いていないのですが、事務局の方が開けてくださったようなので、ありがたく入らせていただきます。
時間までデータの整理を行っていたら、あっという間に授業の開始時間となりました。
最初に昨日行った心理尺度の実験について説明を受けた後、今日予定されていた実験「情報伝達」の実験を行います。
この実験はまあ、ざっくり言いますと
伝言ゲーム
です。

本来は口頭で行ったほうが実験の効果は高いのかもしれませんが、感染予防のため、紙に書いて行うこととなりました。
やり方は、
- 紙に書かれた文章を1回黙読する。
- 読んだら、その紙を裏返す。(もう二度と見てはいけない)
- 30秒カウントする。
- 思い出して紙に書く。
- 自分の書いた紙を次の人に渡す。
これを4回(1グループの実験参加者は4人です)繰り返します。
4人で回すのを1回やってから、文章を変えてもう1回行いました。
1回目は、「○○社のタンカー××号が座礁して海が汚れて、外国の軍隊が救助に駆け付けた」という内容です。
2回目は、「放送大学の心理学実験の授業で、以前は1回でも休むと単位がもらえないので、親せきを次々に危篤にして休んで単位を取った人がいた」というものです。
こんな感じで大筋では伝えることはある程度できる(厳密にはこれも正しいかどうか怪しい)のですが、細部が欠落したり、間違って伝えたりは普通にあります。
1番目の例では、「○○社のタンカー××号」のところ、「〇×号というタンカー」と堂々と書いたのは私です。
2回目の方はある程度書いてある内容のとおりだったのですが、これには理由があります。
1回目は4人中2番目に情報が伝わってきました。一方、2回目は4人のうちの最後に情報が来ました。
1回目はもともとの情報を最初の実験協力者の方が残してくれたので、細かい情報がある程度残っていました。まあ私が捻じ曲げちゃってますけどね。
2回目の方は最後だったので、いい感じに情報の細部がなくなって、(これを「平均化」といいます)覚えやすくなったものが回ってきました。細部では例えば「お父さん」と伝わったところを「父」と書いたりといったゆがみはありますが、1回目に比べれば大したことはないかと思います。
1回目の方も、実はタンカーが座礁して真っ二つになったらしいのですが、その部分は聞いていないし(これも平均化ということになります)、ほかのグループでは木っ端みじんになったところもあるらしいとか。
そんなこんなで楽しい実験はすぐ終わり、昼食タイムです。

午後は、実験結果を集計します。
今回の実験は文章の伝達という、直接数値が出ないものなのですが、文章を意味を基準に細かく区切って1つの要素として、どれだけの要素を伝えられたかを数値化します。

今までと違うのは、相手が文章ということもあり、簡単に○か×かが決められないところがあるということです。例えば、
「11月」というのを、「10月」と伝えたら明らかに×ですが、「11月10日」と伝えたらどうするか。「11月」の部分を〇にして、「10日」の部分を×にするか、「11月」を「11月10日」と間違えて伝えたとして×にするか、なんてことを結構悩みます。
ある程度は講師の先生の指導もありますが、最終的な細かい基準は、実験結果や目的などを踏まえて自分で決めることとなります。
レポートのまとめ方や提出方法の説明を受けながら、それらの整理をしているうちに、あっという間に授業終了の時間となりました。
授業は楽しかったですが、本当の授業というか、単位取得に向けてはこれからのレポートにかかっています。
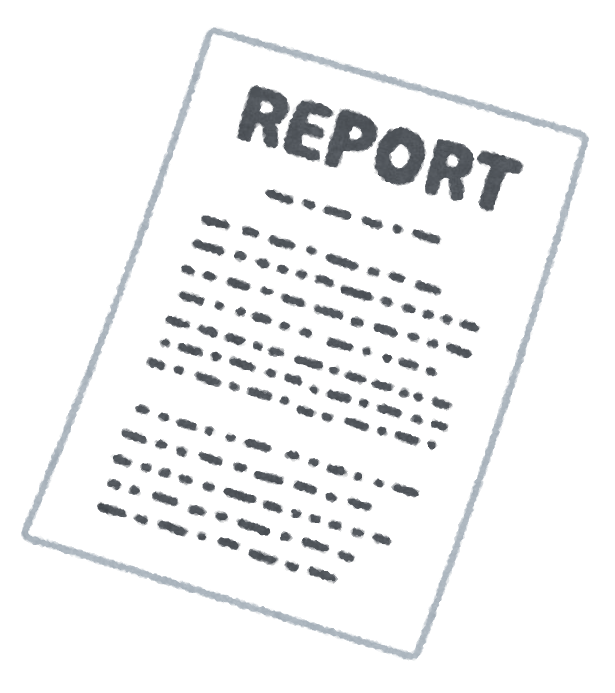
締め切りまで3週間くらいありますが、記憶はどんどん薄れていくので、なるべく早く終わらせたいと思います。
今日はこれから、データの整理をしたいと思います。
では、また。