みなさんこんにちは、ひでえぬです。
たまには金融資産運用設計以外の話題をお送りしようと思い、「成年後見制度」について書き始めたのですが、テーマが壮大すぎて収拾がつかなくなったので、試験前ですし、試験に出そうな内容をお伝えしたいと思います。
というわけで、上場株式の分配金について考えてみたいと思います。
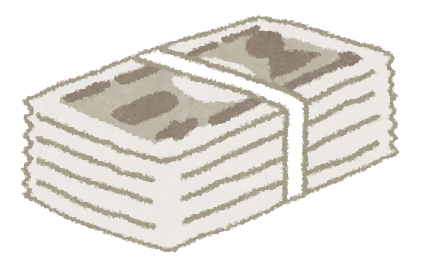
(例題)
ひでえぬさんは、2021年に株式の配当金を受け取ったが、この時の税負担について、申告分離課税を選択した場合と、総合課税を選択した場合の、それぞれの所得税、住民税はいくらか。
給与所得 500万円
配当金 40万円
所得控除の合計額 100万円
- ひでえぬさんの総合課税の税率は、所得是が20%、住民税が10%とする。
- 復興特別所得税は考慮しないものとする。
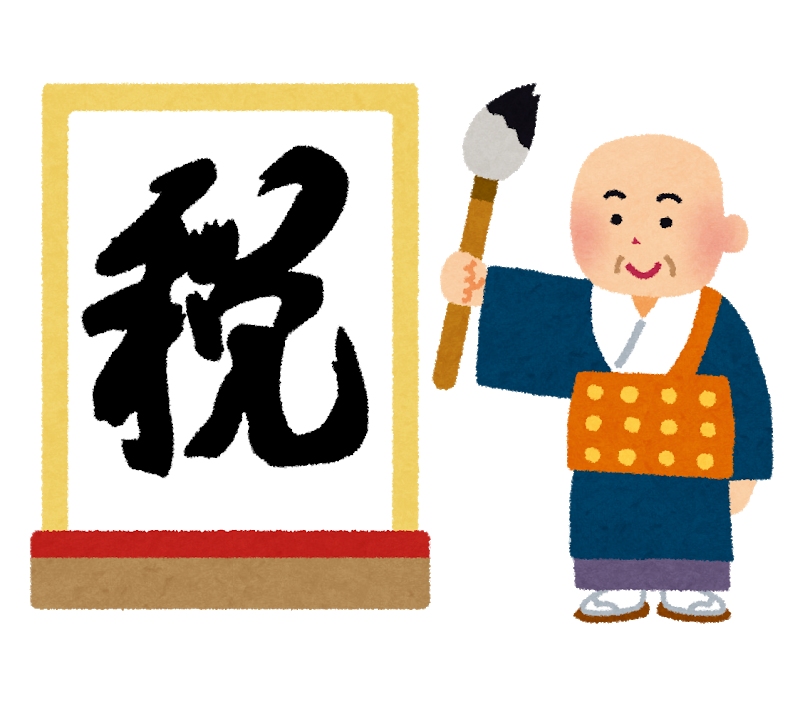
(解説)
上場株式等の配当金については、総合課税と申告分離課税があります。平成29年度の税制改正により、所得税と住民税で異なる申告方法を選択することができるようになりました。
つまり、最も少ない税額となる納税方法を個人で選択できるのです。
では、今回のケースではどのようにしたらよいのでしょうか。
それぞれのケースについてみてみましょう。
(所得税)
ア 申告不要の場合
何もしないとこの方法になります。(源泉徴収ありの特定口座で配当を受け取った場合、受取時に源泉徴収されます。)
この場合の税率は15%ですので、
400,000円×15%=60,000円 ①
イ 総合課税の場合
・税額
この場合、納税者の所得額によって税額が異なることとなりますが、今回の場合、問題文により20%と決められているので、
400,000円×20%=80,000円 ②
・配当控除
所得税において配当所得を総合課税により申告した場合、所得金額が1000万円以下の場合は原則として10%が配当控除として税額控除されます。
よって配当控除額は
400,000円×10%=40,000円 ③
・納める税額
②-③=80,000円ー40,000円=40,000円 ④
①>④ですので、この場合は総合課税のほうがお得ということになります。
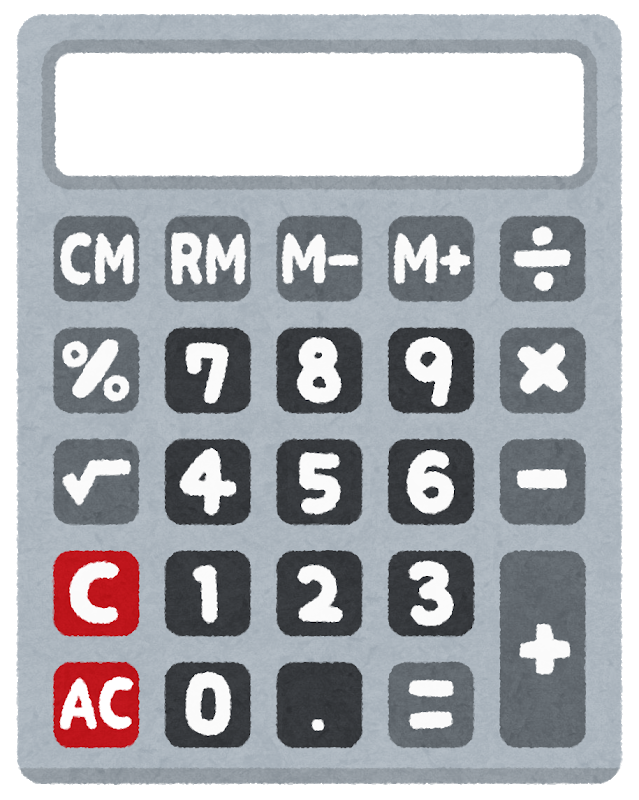
(住民税)
ウ 申告不要の場合
所得税と同様、何もしないとこの方法になります。(源泉徴収ありの特定口座で配当を受け取った場合、受取時に源泉徴収されます。)
この場合の税率は5%ですので、
400,000円×5%=20,000円 ⑤
エ 総合課税の場合
・税額
所得税と同様、問題文により10%と決められているので、
400,000円×10%=40,000円 ⑥
・配当控除
住民税におけるは、所得金額が1000万円以下の場合は原則として2.8%が配当控除として税額控除されます。
よって配当控除額は
400,000円×2.8%=11,200円 ⑦
・納める税額
⑥-⑦=40,000円ー11,200円=28,800円 ⑧
⑤<⑧ですので、住民税の場合は、申告不要を選択するのがベストということになります。
ということで、2018年度以降、CFP資格審査試験ではこの手の問題がよく出題されているようです。
改正後3年を過ぎたので、そろそろ出なくなるかもしれませんが、個人的な予想としては、出ると思っています。
ただ、今回取り上げたのは、その中でも最も基本的なパターンです。
(ひねった問題について)
過去問ではいろんな形でひねっていますが、主なケースでは
・配当控除があると思って実はないケース
配当控除は所得税の場合、「原則」10%と書きましたが、例外もあります。投資信託の普通分配金も総合課税を選択すれば配当控除を受けられますが、「約款上外国公社債を投資対象としている場合」については、その割合に応じて控除される率が変わります。
このため、実は配当控除がないとか、少ないというケースがあります。
・ほかの税目(国民健康保険税など)を絡めてくる場合
市町村で徴収する国民健康保険税は多くの場合所得割を採用しているので、あらかじめ税率を設定したうえで、この税額も含めて答えを求めされる問題も過去に出ています。つまり、住民税を申告分離課税にすると国民健康保険税は増えないが、確定申告することで仮に税率が申告分離課税よりも安くなったとしても国民健康保険税が徴収されるため、そのトータルで判断する必要があったりします。
こんな感じで、問題としては出しやすいというか、まだまだひねる余地があると思うので、しばらくは出るんじゃないかというのが私の予想です。
が、しつこいようですが、出なかったからと言って、怒らないでくださいね。
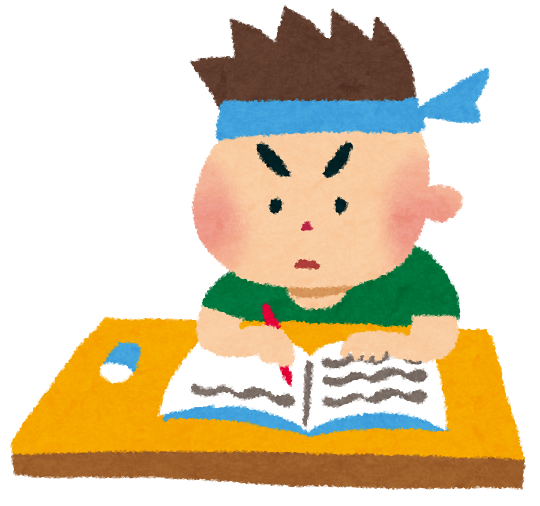
ではまた。